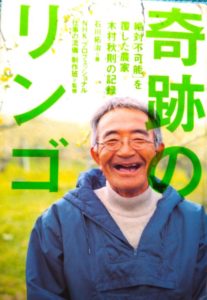最近ある映画を二本観た。
●「死刑に至る病」
●「流浪の月」
どちらも非常に考えさせられる内容でした。
「死刑に至る病」のあらすじは・・・

連続殺人犯「榛村大和」から自分の冤罪を晴らして欲しいと、手紙を貰った「筧井雅也」。
この二人の面会シーンが主軸となって話が進んでいきますが、これは観る人を選びます。
私はこういった作品が元々好きなので大丈夫と思っていましたが、それでも目を覆ってしまう残酷なシーンがありますので「観てね」とは気軽には言えない。
それでも観て欲しいと切に思うのは、この作品が「人の心理」というものを見事に突いているから。「榛村」という猟奇的殺人犯。一見するととても社交的で優しそうな雰囲気を持つパン屋さんの店主。
彼を知る人物が「それでも嫌いになれないんだよな・・・」と、筧井に言った言葉がとても印象的だった。そう・・・人の「好き・嫌い」は事の「善・悪」に比例しないのだ。
「好い人だから好き」
「悪い人だから嫌い」という様に人の「感情」は単純には図れない。
死刑判決を受けた「榛村」をTVのニュースで観た人はおそらく、全員が彼の事を嫌いになるだろう。しかし彼を身近に知る人は必ずしもそうはならない。
そしてそれはもう一人の主役「筧井雅也」にも通じる。
※ここからはネタバレを含みますので、ご注意下さい。↓↓
彼が「冤罪」だと訴えていた事件を調べ始めた「雅也」は、三流大学に通う地味で目立たない青年。中学時代、塾に行く前に榛村のパン屋に通っていたという過去から、今回の調査に乗り出した。
はじめは「頼まれたから・・・」といった風だったが、榛村との面会を重ねていく内に彼の中の何かが変化していった。彼の家庭環境は絶対権力を奮う父と、何事も自分で決められない母との温かみのない生活に鬱々としていた。
子供の頃には父からの「虐待」も受けていた。そんな成育歴から、雅也は自分の感情を「抑圧」する事に慣れきっていた。
そんな彼が「榛村」と関わる事で「変貌」していく。榛村は、証拠を集め報告に来てくれる雅也を労い「凄いよ」と笑顔で褒め称える。雅也の表情が徐々に明るくなり、生気と自信に満ち溢れたように変わっていく。
そして、これまで「抑圧」されてきた感情がある日突然爆発する。相手はたまたま肩がぶつかった中年のサラリーマン。その男に悪しざまに罵られた雅也は激高し、追いかけて傘で殴りつけるという行動を起こした。かつての彼なら「抑圧」していただろう。
たった一人の人間との関わりで人は簡単に「変われる」のだ。それが「榛村大和」という人間の持つ「人心掌握術」である事を彼は知らない。榛村の依頼に応える事で「自尊心」を取り戻し、自信を持ち始めた「雅也」。
彼らを観ているだけで恐ろしくなった。人はこうも簡単に「操作」され「利用」されてしまう。そして当の本人はそれを自覚していない。「自分は自分の意志で行動している」という「思い込み」がそこに潜んでいる事に気付かない。
ここがこの映画の「肝」であり、真の「恐怖」だと私は思った。
榛村のような人間に出会い、何かを頼まれてその度に賞賛の言葉を貰ったら、誰でも「雅也」のように彼に尽くしてしまうだろう。
そういう意味でこの映画は「面白い」
そしてもう一本の映画が「流浪の月」ですが、ここまで長丁場になってしまったので、
こちらについては次回へ続く事に致します^^♪